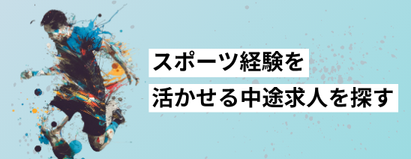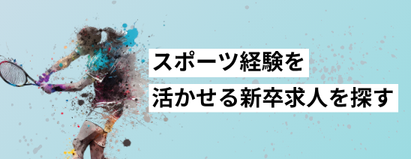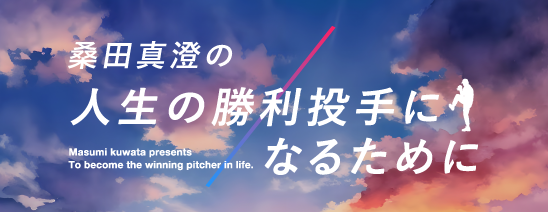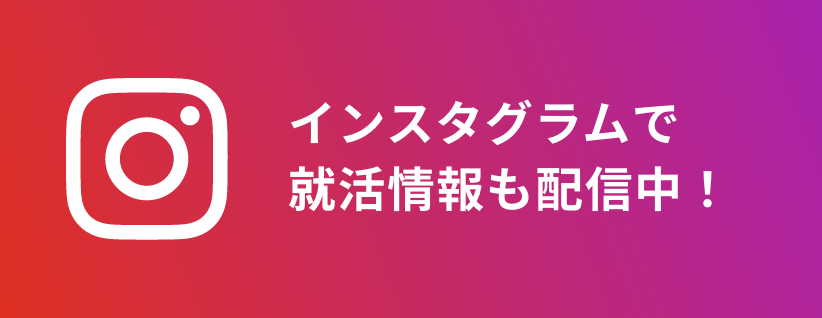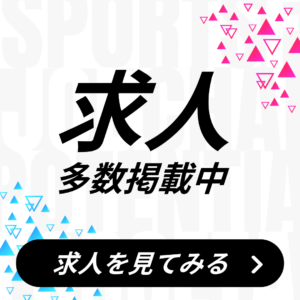2024.10.22
釣り関係の仕事6選!有利になる資格や仕事の探し方をご紹介
趣味で釣りを楽しむ人はたくさんいますが、仕事にするという選択肢もありますね。本記事では、釣り関係の仕事や、必要な資格、適性についてまとめました。
釣り関係の仕事に興味がある方は、ぜひ最後までご覧ください。
INDEX
釣り関係の仕事6選

「釣りをどうやって仕事にするの?」と疑問に思う人も多いでしょう。
実は、釣りに関連する職業は多岐にわたります。ここからは、釣りに関する6つの仕事の具体例をご紹介します。
プロアングラー
プロアングラーとは、釣りの競技大会やトーナメントに参加し、技術と知識を駆使して賞金を稼ぐ仕事です。
スポンサー契約や広告収入も重要な収入源となるため、技術だけでなく自分の名前を広めるためのセルフプロモーションやSNS運用も重要となります。
プロアングラーになるためには、地域の大会に参加して実績を積み重ね、スポンサーを獲得するのが一般的です。
競技のスキルに加え、釣りに関する豊富な知識や、新しいテクニックを追求する情熱が求められます。
また、釣りの映像を通じて技術をアピールする機会も増えており、動画編集やカメラ操作のスキルもあると有利になるでしょう。
フィッシングガイド

フィッシングガイドは、釣りを楽しむ人々に対して、釣り場の案内や技術指導を行う仕事のことです。地域の釣り場や魚の生態に精通していないと、案内や指導ができません。
観光客相手のガイドとして活躍することもあり、コミュニケーション能力や接客スキルも重視されます。
特に海での釣りガイドを行う際は、小型船舶免許や海に関する知識が必須となります。
季節ごとの釣れる魚の種類や、釣りのベストシーズンを把握していることで、リピーターを増やすことを期待できるでしょう。
釣具屋

釣具店での仕事は、釣り具や用品の販売や道具のメンテナンスなどが中心です。
また、店によっては客に対してアドバイスや講習会などを行ったり、釣りイベントを開催することもあります。
最適な商品を提案したり釣りのテクニックについてもアドバイスしたりすることもあるため、自身も釣り経験者、もしくは釣り好きであることは必須条件です。
釣具の修理やカスタムサービスには、製品の知識や修理技術も必要です。
また、釣りにもトレンドがあるため常に最新情報にアンテナを張ったり、製品のメリットや使い方をしっかりと理解していることが強みとなります。
釣りに対して豊富な知識を持っている店員は、顧客との信頼関係も築きやすいでしょう。
製品を制作・販売

釣り具やアクセサリーを手作りして販売する仕事もあります。
オリジナルのルアーやハンドメイドロッド、フィッシングウェアのデザインなど、他にはない個性的な製品を作りたいという思いを持っている人に適した仕事です。
個人事業主として開業したり、法人化して事業を展開したりする選択肢があります。
また、オンラインショップを開設したり、SNSで自作の製品を宣伝したりすることで、ファンを増やしていくこともできます。
制作・販売分野では、釣り具に対する理解だけでなく、マーケティングや商品開発の知識も重要です。
製品の品質やデザインにこだわるだけでなく、顧客のニーズを捉えた製品を生み出すことが、成功のカギとなるでしょう。
メーカー・釣り業界

釣り具メーカーや関連企業で働くことも、釣りを仕事にする一つの道です。製品の企画・開発から営業、マーケティング、カスタマーサポートまで、様々な部門があります。
自分自身が釣りに対して情熱を持っているほど、釣り人の視点に立った商品開発やプロモーションが可能になります。
製造現場やテクニカルサポートに携わる場合は、釣り具に関する技術的な知識や、細かい作業が求められることもあるでしょう。
一方、営業やマーケティングでは、釣り具の魅力を的確に伝えるプレゼン能力や、業界全体のトレンドを掴む力が必要です。
メディア運営

釣りに関するブログやYouTubeチャンネル、SNSアカウントなどを運営して収益を得ている人もいます。
釣りのテクニック紹介、製品レビュー、釣り場レポートなど、コンテンツを通じてファンを増やし、広告収入やスポンサー契約を得ることが可能です。
最近では、映像制作のスキルが重視され、特にYouTubeなどでの動画配信が収益源となることが増えています。
釣り場での臨場感あふれる映像や、役立つ情報を提供することで、多くの視聴者を獲得することができるのが魅力です。
釣り関係の仕事をする上で有利になる資格
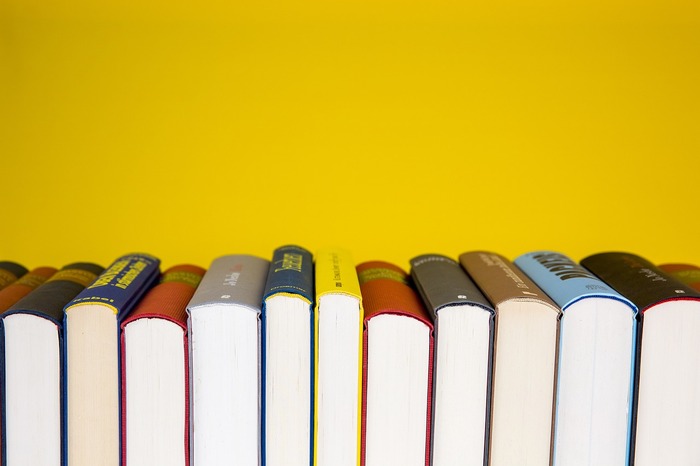
釣り関係の仕事は基本的に資格がなくても問題ありませんが、関連資格を取得することでスキルや知識の証明ができます。
ここでは、釣り関係の仕事をする上で有利になる人気の資格を2つご紹介します。
公認釣りインストラクター

一般社団法人 全日本釣り団体協議会(通称「全釣り協」)が認定する資格です。協会が主催する講習会を受講し、試験に合格することで資格を取得できます。
釣り場を取り巻く自然環境の悪化や釣りマナーの低下・ルールの認識欠如による釣り場の環境破壊といった問題が顕在化する昨今、安心して釣りを楽しめる環境をつくる目的で、この資格が生まれました。
インストラクターの役割は、一般の人を対象に釣りの技術や水産資源の保護や環境保全、安全確保、マナー・ルールなどの指導を行うこと。
漁業者とのトラブルや海難事故の発生防止にも期待されています。各種釣り大会等の講習会の講師として出席することもあります。
| 取得条件 | 満20歳以上の者 |
| 費用 | ・受講受験料 20,000 円 ・登録料 10,000 円 |
参考:全日本釣り団体協議会
小型船舶操縦士免許

「小型船舶操縦士免許」は国家資格です。自分が船を操縦して釣りをする、もしくは釣り客を船に乗せて海釣りをする場合などにはこの資格が必須となります。
小型船舶操縦士免許には以下のの4種類があり、基本的には操船場所や陸岸からの距離で資格の種類位が区分されているのが特徴です。
- 一級小型船舶操縦士免許
- 二級小型船舶操縦士免許
- 二級小型船舶操縦士(湖川小出力限定)免許
- 特殊小型船舶操縦士免許
取得する場合は、仕事内容に合わせて種類を選びましょう。
| 国家試験の受験条件 | |
| 年齢 | 一級船舶免許:満17歳9か月〜 二級船舶免許、湖川小出力限定免許、特殊小型船舶免許:満15歳9か月〜 ※それぞれ満18歳、満16歳になった日から免許を手にすることが可能。 |
| 視力 | 両眼とも0.5以上であること。(矯正可) |
| 色覚 | 夜間において船舶の灯火の色を識別できること。 |
| 聴力 | 5メートル以上の距離で普通の大きさの声音の弁別ができること。(補聴器可) |
参考:国土交通省
釣り関係の仕事に必要な適性は?

釣り関係の仕事をする上で「釣り好き」なことは必須条件ですが、その他にも必要となる適性があります。
ここでは、釣り関係の仕事に必要な適性についてご紹介します。
情報収集が上手い
釣りは、自然環境や天候に大きく左右されるアクティビティです。
魚の行動パターンや水温、潮の流れ、天気など、さまざまな要因を考慮しながら、最も効果的な方法で釣りを行う必要があります。
このため、釣りの仕事に従事する人は、常に最新の情報を収集し、状況に応じて適切な判断を下すスキルが求められます。
たとえば、プロアングラーやフィッシングガイドでは、魚の移動や釣り場のコンディションに関する知識を持っていることが顧客満足度や釣果に大きく影響します。
釣具店でも、製品や釣法に関する最新のトレンドを把握し、顧客に的確なアドバイスを提供できるようになることが重要です。
情報収集をする際はインターネットやSNSを活用して、業界内外の動向を素早くキャッチしましょう。
特にメディア運営を行う場合は、独自の情報源があると有益なコンテンツを発信できます。
手先の器用さや正確性がある

釣具店での修理業務や、オリジナル釣具を制作する場合、どれだけ丁寧に、そして正確に作業を進められるかが重視されます。
釣具の制作や修理を行う際には、手先の器用さと正確な作業が求められます。
特にルアーやロッドの製作、ラインの結び方など、釣り具のメンテナンスは非常に細かい作業が必要となります。
製品開発や品質管理を担当する場合、製品の細部に目を配り、わずかな欠陥や不備にも気づく観察力と慎重さが重要です。
また、フィッシングガイドの仕事をする際にも、顧客が釣りを楽しめるよう、釣具のセッティングやトラブル対応を迅速に行うことが求められます。
オリジナリティのある価値を提供できる

観光業や製品開発、メディアに携わる場合、他と差別化された独自の価値を提供することが成功の鍵となります。
顧客が欲しいと思う機能やデザインを取り入れたユニークな商品開発、釣り場のレポートや釣果の分析など、「今、何が求められているのか」を敏感にキャッチすることがポイントです。
釣りの知識や経験をベースに、自分だけの視点を持ち続けられる人はこの業界で成功しやすい人かもしれません。
釣りが上手くなくても釣り関係の仕事に就ける?

釣り関係の仕事に興味があるものの、「自分は釣りがあまり上手くないけれど、働けるだろうか?」と不安に感じている人もいるかもしれません。
結論からいうと、釣りのスキルが高くなくても釣り関連の仕事に就くことは十分に可能です。
釣りの技術に自信がない場合でも、他のスキルや適性を強化し、自分に合った釣り関係の仕事を見つけることはできるのでご安心ください。
釣りの実践的な技術は役立つ一方で、仕事の種類によってはそれほど重要ではない場合もあります。
例えば、最新の釣り具のトレンドや、どのような製品がどの釣りスタイルに適しているのかを理解していれば、顧客やクライアントに的確なアドバイスを提供できます。
また、SNSの運用や広告の企画・実行では、釣りに対する情熱は必要でありながら、マーケティングの知識やデジタルスキルが重要となるでしょう。
中には直接的に釣りのスキルが求められる職種もありますが、初心者として働きながら釣りの技術を学んでいける環境もあります。
特にフィッシングガイドや釣具店では、先輩から釣り技術を教わる機会も多いため、実践経験を積みながらスキルを向上させることができます。
釣りが得意でない人でも、学ぶ意欲があればスキルを伸ばすことは可能です。また、釣り好きであれば、趣味を続けるうちに自然と技術も向上していくでしょう。
釣り関係の仕事の探し方

釣りを仕事にしたいと思っても、具体的にどこでどうやって仕事を探せばよいのか悩む人も多いでしょう。
釣り関係の仕事は、他の業界に比べて求人情報が少ない場合もありますが、適切な探し方を知っていれば、仕事に就けるチャンスはあります。
ここでは、釣り関係の仕事を探すための具体的な方法をいくつか紹介します。
インターネット・SNS

現在、インターネットは仕事探しにおいて最も便利で広く使われるツールです。専門的な求人サイトや、釣りに特化した掲示板、SNSでの情報収集が有効です。
釣具メーカーや釣りガイドサービスは、SNSを通じて求人情報やイベントスタッフの募集を行っていることがあります。
釣り好きな人たちが集まるコミュニティやグループに参加することで、求人情報が回ってくることもあるため積極的にSNSを活用しましょう。
また、釣り関連のYouTubeチャンネルやブログを運営している企業や個人も、SNSで仕事の募集やコラボレーションの機会を提供することがあるので、フォローしておくと有益な情報を得られるかもしれません。
学校からの紹介

フィッシングガイドや釣り関連の仕事を目指す場合、関連する専門学校や講座を受講し、そこから紹介を受けるという方法もあります。
釣りやアウトドアに関する専門学校や職業訓練校では、釣具メーカーや釣り関連の企業と連携しており、学生に対してインターンシップや求人の紹介を行うことがよくあります。
また、釣りのインストラクターや小型船舶免許を取得する際に、資格取得の講座から直接求人が紹介されることもあるでしょう。
釣りに関連する資格を持っていると、釣りガイドやインストラクターの仕事に応募する際に有利になります。釣り関係の学校に入学することも、キャリアの第一歩です。
知人からの紹介

知人や釣り仲間からの紹介で仕事の縁がつながる場合もあります。
釣りはコミュニティが大切な趣味でもあるため、釣り好きの人たちと積極的に交流することで、仕事のチャンスが広がります。
釣りイベントや地元の釣りクラブ、SNSのコミュニティなどに参加して人脈を広げておくと、仕事の紹介を受ける機会が増えるかもしれません。
特にフィッシングガイドや釣具店のスタッフなどの仕事は、信頼できる人からの紹介や、知り合いのつながりで採用されることが多いです。
釣りの経験が少ない場合でも、釣り好きの人たちとのネットワークを通じて、新しい機会が見つかる可能性があります
エージェントサービスの活用

スポーツやアウトドアに特化した転職エージェントサービスを利用するのも一つの方法です。
「スポーツフォースタレント(旧アスリートエージェント)」は、体育会人材の支援を得意とする転職エージェントです。
釣りをはじめ、アウトドアやスポーツ関連の仕事を探している場合は、ぜひ登録してみてください。
インターネット上では公開されていない非公開求人を紹介してもらえることもあります。面接対策や履歴書の添削も行ってくれるため、初めての就活でも安心ですよ。
おすすめの転職エージェントに関しては、以下の動画でも解説しています。ぜひチェックしてみてください。
こちらの記事もおすすめ
体育会・スポーツ学生向け就活エージェント・就活サイトのおすすめ10選!選び方も解説
まとめ
ご紹介したように、釣り関係の仕事には釣りに直接に関わる仕事から間接的に関わる仕事まで、様々な種類が存在します。
就職先探しで悩んでいる方は、ぜひスポーツフォースタレント(旧アスリートエージェント)をご利用ください。キャリアカウンセラーが親身になってあなたの就活の相談に乗ります。
もちろん登録・利用は無料です。「まずは何からスタートしてよいか悩んでいる」という方も大歓迎ですので、お気軽にご相談くださいね。
スポーツフォースタレント(旧アスリートエージェント)とは?
スポーツフォースタレント(旧アスリートエージェント)は、アスリート・体育会&スポーツ学生に特化した就職・転職エージェントです。
創業以来、
といった業界でも高い数字を出しているのが特徴です。
就職の知識が全くない方でも、元競技者であるキャリアアドバイザーが手厚くサポートいたします。
履歴書の書き方から面接のアドバイスまで、スポーツと同じように「勝つまで」全力で支援させていただくのがモットーです。
利用は完全無料です。私たちと一緒に就活でも勝利をつかみ取りましょう!
ARTICLE
関連記事
CAREER INTERVIEW